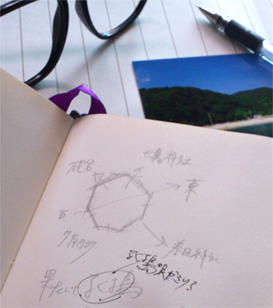Exhibitions
まもなく、死を迎える可能性のある家。
選択したつもりは無い。
しかし、結果この家で、10年以上家族と生活をした。
その時間は消すことのできない記憶として 、私の中に刻み込まれた。
家の中で私は確実に、存在を認められていた。
家族というコミュニティの子供の役柄を与えられ、振る舞うことに、何の疑問も感じなかった。
家から飛び出した後、私の役割は消失した。
私は、あの家にとって死者となった。
帰っても、そこに居場所はなく、まるで客として扱われた。
一度離れると、役割は取り消され、もう戻ることはできなかった。
例え、家族が居ようとも、住まない人間はコミュニティに入ることができなくなる。
血の関係など、書類上のものに過ぎず、距離は関係を分断する理由になり得る。
そして、父が亡くなり、その崩壊は加速する。
無理矢理繋いでいた円は一気に崩れ、皆この家を出ていった。
脆い絆で繋がれていた家族は、それぞれ別の世界に旅立った。
あの世や、東京や、大阪に。
家にとっての私達家族は死んだ。
今この家に住むものは居ない。
脱け殻のような家になってしまった。
久々に家を訪れた私は、その空虚な空間にまだ少しだけあの頃の記憶が残っているのを感じた。
それは、ただの追体験なのかもしれない。
しかし、その記憶は私を圧倒し、凝縮された10年近い年月を走馬灯のように走らせた。
あの頃にはもう戻れないとは理解しつつも、戻りたいと思った。
唯一存在価値が認められていた、あの時代に。
家に再び息を吹き込むことは可能なのだろうかと考えた。
この家が最後に輝く為に、喩え偽物であっても魂を込めなおし、一番美しかったころの記憶を再現できないだろうか。
そして、回帰することの不可能を自らの魂に刻み付け、二度とうしろを振り向かないように。
ある家が、失われた家族と再会する、最期の季節。
その刹那、時間は失われ、彼岸と此岸が邂逅する。
2012年4月27日、父、松岡洋の命日、一夜、家は開かれる。
松岡 友
高知県の鵜来島を舞台に、そこに伝わる歴史や説話を下敷きとした同名小説の世界を追体験しつつ、謎を解く鍵として出展者たちの作品に接し、未完の作品世界を補完していく——
以上のように、この「るくる島黄金伝説」のあらましを祖述すると、現代アート界に既に定着して久しいサイトスペシフィックというコンセプトや、近年オタク文化界を越えて注目を集めている〈聖地巡礼〉というムーヴメントの一つの応用−流用例として受け取る向きもあるかもしれない。
しかしこのイベントの射程は以上のような近年の諸動向との表面的な類似というところとは別のレヴェルから測られなければならないだろう。ここにおいて目指されているのは、現実の場所を体験することと小説の世界を追体験することとが一致しているという状態であり、さらに言うと、小説/物語の世界の変容が現実の場所のあり方や様態を変容させるという経験である。そこでは作品は単にその場に置かれた物であることをやめ、世界そのものに意味があるというアレゴリー的思考へと私たちを導くことになる。アレゴリーを通して、私たちは世界を拡張させ、現実を変える契機をつかむことができる。
かつて大江健三郎は『万延元年のフットボール』において、愛媛県の山村を伝統と近代、過去と現在、現実と超現実といった要素が交錯する場として描き出し、登場人物たちの変容を通して、これらの要素が複雑に絡み合って閉塞している日本という場所の変容を試みた。この「るくる島黄金伝説」もまた、そのようなアレゴリカルな物語を通して現実を変容させる試みにほかならない。
(text: 前田 裕哉)
「セレンディピティの扉」
きっと、始めに物語が在った。
あなたは、自己の意識が身体の何処に格納されているのか?という言及を自身へ投げ掛けた事は無いだろうか?
前提として、本当に、身体内に意識は格納されているのだろうか?
身体の生成以前に意識が存在し、寧ろ、その意識の素粒子こそ、身体を生成する質量を伴った情報だとしたら?
その意識は、身体を俯瞰するラグランジュポイントに静止していないだろうか?
時空間や物体の生成以前、無に誕生した、やがて意識と真名される物語の原始は、神代における飯事として増幅を繰り返しながら、あなたの二重螺旋に保存されている。
二○十一年八月、貨幣経済の全滅としての未来に恐怖する国家を嘲笑するかのように、限界集落の孤島に上書きされた現実の原始「るくる島」にて開現した「るくる島黄金伝説」は、物語と現実の次元域を流麗に移動しながら、人間本質の本来の営みとして、二重螺旋の深淵で呼吸する神話へのエンカウントを試みた。知覚の狭間で、意識は現実外現実と交信し交換し、既存の階層を跳躍する。それは、自己と他者、内界と外界を呼応させる装置として機能した。まるで、変調する存在証明を回復するように。
永遠に眠り続けるかも知れない身体を、意識はそっと揺り起こす。
二○十一年十月、豊穣なる作家のフラグメントとして「るくる島」は継続する。身体が認識し得る次元領域、現次元に幽閉された神話の種子を解放するため、逆位相からのオーバーレイを時空間へ加法する。深淵に覗かれ始めたプレイヤー/キャラクターは、俯瞰する鑑賞者の意識を同次元へ召喚し、それこそが、かつての未来として描かれていた、現実への美しい消失点であり、身体外意識と高次元領域を紡いだ、新世紀の飯事⇔神事へのヒューマン・コンパスとなる。現実に抵抗する物語の括弧が、美しく上書きされた幻想現実のフィールドとして誕生する。
きっと、終りに明日が在る。
(text: 真名井 良秀)